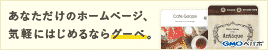ブログ
経験からの変化
最初の就職先は総合病院でした❗
総合病院なので、整形外科、脳神経外科、外科、内科など、
さまざまな診療科からリハビリの処方が出ます。
当時は理学療法士や作業療法士がまだ少なく、担当する患者さんの
人数も多い状況でした。
さらに、スタッフが休めばその分の患者さんも診なければならず、
入院患者さんはもちろん、外来患者さんも担当するという忙しい
毎日でした💦
今では療法士の数も増え、急性期・回復期と担当が分かれていますが、
当時は急性期から慢性期まで全て対応しなければならず、若い療法士の方々
には想像できない環境かもしれませんね😅
そんな大変な状況でしたが、逆に多くの症例を経験できるチャンスでもありました。
限られた時間でどう変化を出すか、幅広い年齢層の患者さんとどうコミュニケーションを
取るか、日々考えながら取り組んでいました。
その中で気づいたのが、勉強の大切さです。学生時代は大嫌いだった勉強も、
患者さんのために必要性を感じ、文献を読んだり研修に参加したりするようになりました✍️
その辺りから不思議なことに、何度聞いても頭に入らなかった教科書の内容が、
スッと理解できるようになり、次第にこの仕事の楽しさを感じるようになっていきました😄
その後は学会発表や各種研修会に積極的に参加し、気づけば研修会を企画したり、
講師として登壇したりする立場に。人は環境によって変わるものだと、実感しています🤣
実習での衝撃的な学びで目から鱗
私が養成校3年生だった頃、実習で訪れた東京の病院は、全国的にも先駆けて訪問リハビリを行っている施設でした。当時はまだ介護保険制度もなく、学校の授業でも「訪問リハビリ」や「在宅リハビリ」という言葉すらほとんど聞いたことがありませんでした。
その病院での実習初日に「患者さんを診る際に大切なことは何?」と質問され、私は教科書的な答えをしました。つまり「筋力や歩行の安定性を評価し、問題点を見つけて治療し、出来るだけ早く自宅へ復帰させることが大切」と。しかし、指導者から返ってきたのは意外な言葉でした。
「それは本人が本当に望んでいること?それでその方は幸せなの?」
最初は何を言われているのか分かりませんでした。しかし続けて「なぜ筋力が必要なの?なぜ歩けなければならないの?」と問いかけられました。さらに、「どんな場面で、どのくらい歩くのか?そのためには何が必要なのか?それが今出来ない理由は何なのか?こうした視点があって初めて、筋力や歩行能力を評価する意味が出てくるのでは?」と指摘されたのです。
加えて、「退院のために必要なのは、身体機能だけではない。家庭環境、家の周囲の状況、家族関係、退院後の生活、経済状況など、さまざまな要素を知った上でなければ、適切なリハビリを進めることはできないよね?」と言われました。これまで全く意識していなかった視点を突きつけられ、私は大きな衝撃を受けました。正に目から鱗でした!
この経験を通して、「リハビリは身体機能を改善することだけが目的ではなく、その人がどのような人生を送りたいのかを考えることが大切なのだ」と気づかされました。身体だけを診るのではなく、その人の役割や目標を理解しなければ、本当のリハビリにはならない…そのことを痛感した瞬間でした。
この実習を機に、訪問リハビリに対する関心が高まりました。しかし、岩手に戻り就職してからは、訪問リハビリを実践する機会はなかなか得られませんでした。理学療法士になって10年後に介護保険制度が始まるちょっと前まで、その「訪問リハビリ」という言葉すら身近にない状況が続いたのです…。
何故、理学療法士を目指したの❓
理学療法士という職業を知ったきっかけ
高校2年生になるまで、「理学療法士」という言葉はもちろん、「リハビリ」という言葉すら知りませんでした。
きっかけは、ラグビーの練習で腰を痛めて整形外科に通院したことでした。腰椎牽引や低周波治療などの物理療法を受けている横で、誰かが患者さんの身体を動かしたり、動作の指導をしている姿が目に入りました。
「マッサージでもないし、医師や看護師でもなさそう…これは一体、どんな仕事なんだろう?」
気になって調べてみたところ、そこで初めて「リハビリテーション」という分野と、「理学療法士」や「作業療法士」といった職業の存在を知りました。
……ただ、後から知ったのですが、そのとき患者さんを担当していたのは、実は理学療法士ではなく柔道整復師の方だったんですけどね(笑)
それでもその出会いが、私の進路を大きく変えるきっかけになりました。
当時、リハビリの養成校は東北に3校しかなく、そのうちの1校が岩手にあることを知り、そこから志望を工学系の大学からリハビリ系の専門学校へと変更。
なんとかギリギリ(?)で 岩手リハビリテーション学院 理学療法学科 に合格し、私の理学療法士への道がスタートしました。