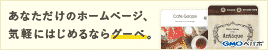ブログ
四十肩・五十肩
夜も眠れないほどの肩の痛み、もう我慢しなくていいんです。
国家資格を持つセラピストが徹底サポート!硬くなった肩を「動かせる肩」へ。
✅こんなお悩みはありませんか?
- 洋服を着替えるのがつらい
- 夜間、ズキズキして眠れない
- 髪を結ぶ・背中をかく動作ができない
- 放っておけば治ると思っていたが悪化してきた
- 病院では「炎症が収まるまで様子見」と言われた
自然に治るケースもありますが、関節の硬さが残ると後々の動きに支障をきたすことも…
👨⚕️理学療法士の資格を持つセラピストが「痛み+動きの制限」をしっかり評価してアプローチ!
- 炎症期・拘縮期・回復期など、段階ごとの適切な施術
- 肩だけでなく、肩甲骨・姿勢・胸郭の連動まで見るからこそ改善へ
- 「自分で出来るケア&トレーニング」や「日常での注意点」もしっかりアドバイス
💡なぜ当院で改善するのか?
- 肩の動きに特化した専門評価と手技
- 理学療法士の国家資格保有者だからこそわかる“回復の道筋”
- リハビリと整体の融合プログラム
💡もう「仕方ない」とあきらめる必要はありません。
痛みや不調は、体からの大切なサインです。医学的な知識と経験を持つセラピストだからこそ、本当に必要なケアが可能です。
一時的な改善ではなく、「もう同じことで悩まなくていいカラダ」を一緒に作っていきましょう!
頭痛
慢性的な頭痛にお悩みの方へ
薬に頼らず、頭痛の原因を根本から見直してみませんか?
✅こんな頭痛で悩んでいませんか?
- デスクワーク中にこめかみがズキズキする
- 首や肩のコリとセットで頭痛が起きる
- 眼精疲労から頭が重い
- 病院では「異常なし」、でもつらい
- 市販薬を飲み続けるのが心配
その頭痛、首・肩・背中の筋肉や姿勢が原因かもしれません!
👨⚕️理学療法士の資格を持つセラピストが行う「姿勢×自律神経」への整体アプローチ
- 頭痛のタイプ(緊張型・姿勢性など)を見極めた施術
- 猫背やストレートネック、噛みしめグセなども分析
- 呼吸の浅さや自律神経バランスにも着目!
💡薬だけに頼らない、新しい頭痛対策とは?
- 根本原因から整える体質改善整体
- 国家資格保有のセラピストだからこその医学的知識と技術、安全に配慮した施術による安心感
- 自宅でできる簡単ストレッチやセルフケアも指導
- 日常生活における注意点などもしっかりとアドバイス
膝痛
歩くのがつらい…その膝の痛み、放置していませんか?
理学療法士の資格を有するセラピストによる本格整体で、手術・注射に頼らない根本改善を目指しませんか?
✅膝の痛み、こんなお悩みありませんか?
- 階段の上り下りで膝が痛い
- 正座ができなくなってきた
- 病院では「年齢のせい」と言われてしまった
- 薬や注射を繰り返しているが改善しない
- 将来、歩けなくなるのでは…と不安
その痛み、膝だけが原因とは限りません!
👨⚕️病院勤務経験あり!国家資格を持つ理学療法士が根本からアプローチ
- 姿勢や歩き方、股関節や足首との関係まで評価
- 筋力や柔軟性、関節の動きを細かく分析
- 「いま膝に何が起きているか」「どうすれば膝がラクに動くか」などをわかりやすく説明・施術
💡当院が選ばれる理由
- 科学的根拠に基づいた、安心・安全の施術
- 一人ひとりの生活動作を考えた再発予防プラン
- 自宅でできるセルフケア指導も充実
💡もう「仕方ない」とあきらめる必要はありません。
痛みや不調は、体からの大切なサインです。医学的な知識と経験を持つセラピストだからこそ、本当に必要なケアが可能です。
一時的な改善ではなく、「もう同じことで悩まなくていいカラダ」を一緒に作っていきましょう!
腰痛
身体の悩みで、肩こりと共に常に上位にランキングされる腰痛
本気で腰痛を根本改善したいあなたへ
医学的根拠に基づく整体で、慢性的なつらさとさよならしませんか?
✅「どこに行っても良くならなかった腰痛」こんなお悩みありませんか?
- 朝起きると腰が重だるくてつらい
- 長時間のデスクワークや運転で腰が痛む
- 整形外科で「異常なし」と言われたけど、痛みは続いている
- 湿布や薬でごまかしているだけの毎日に不安を感じている
- 一時的に良くなっても、すぐに痛みがぶり返す
もし一つでも当てはまるなら、当院の施術があなたの力になれるかもしれません。
👨⚕️国家資格の「理学療法士」を持つセラピストがあなたの腰痛を徹底的に分析・施術
当院のセラピストは、国家資格の理学療法士免許を保有し、病院やクリニック、スポーツ現場などで多くの経験を積んでおります。
その場しのぎのマッサージではなく、「なぜ腰痛が起きているのか?」を明確にし、根本的な改善を目指します。
💡医療現場と同レベルの評価・アプローチをあなたに
- 姿勢・歩き方・体の使い方のくせをチェック
- 関節・筋肉・神経の動きを詳細に評価
- あなたに合ったセルフケアや運動指導もサポート
だからこそ、「ずっと悩んでいた腰痛が楽になった!」という声を多数いただいています。
📈当院の腰痛アプローチが選ばれる3つの理由
① 医学的根拠に基づいた安心・安全な整体
国家資格を持つセラピストが科学的な評価に基づき、丁寧に施術を行います。
② 痛みの「根本原因」を見つけてアプローチ
痛みの原因は腰だけとは限りません。姿勢や関節の状態、筋力のバランスなどの全身状態を総合的に見ていきます。
③ あなた専用のセルフケア&再発予防まで
再発しない身体を目指して、わかりやすく続けやすいセルフエクササイズもお伝えします。
🧘♂️もう腰痛で悩む日々を終わりにしませんか?
慢性的な腰痛は、放っておいてもなかなかよくなりません。でも、正しい知識と方法があれば、良い方向へ向かいます。
本気で「腰痛を根本から良くしたい」と思う方、ぜひ一度ご相談ください。あなたの人生が変わる第一歩を、全力でサポートします。
肩こり
身体の悩みランキングのいつも上位に来る「肩こり」
◎その肩こり、本当に痛みが出ている場所だけの問題でしょうか?実は“姿勢”、“体の使い方”、“内臓”、“体質”などから来ているかもしれません!
国家資格である理学療法士でもあるセラピストが、“根本原因”からアプローチします👍
◎なぜ、肩こりはこんなにも多いのでしょう?
現代人の多くが抱える「肩こり」。その原因は単純な筋肉疲労ではなく、以下のような複合的な要因が重なっています。
🔍 肩こりのメカニズム:あなたの体で、こんなこと起きていませんか?
▶ 長時間のスマホ・パソコン作業で…
✔ 首が前に出た「ストレートネック」に
✔ 肩が前に丸まる「巻き肩」状態に
✔ 背中が丸くなり、筋肉のバランスが崩れる
▶過去に足のケガなどをして
✔ 立位や歩行が不安定である
✔ その不安定さや痛みのために緊張している
▶ その結果…
首や肩の筋肉が引っ張られ続けて緊張しっぱなしに
筋肉への血流が悪くなり、老廃物がたまるなどで、いわゆる“こり”発生
姿勢を支えるインナーマッスルが働かず、表面の筋肉に過剰な負担
頭を支えるために、肩・首・背中ががんばりすぎて慢性的なだるさや重さが発生
💡 つまり、肩を“揉むだけ”では根本改善できないのです
肩こりを根本から良くするためには、姿勢や動作のクセを見直し、 使いすぎている筋肉を休ませることと、
上手く働いていない筋肉を正しく使えるように整えることが重要です。
🧠そこで選ばれるのが、病院やクリニックで、数多くの肩こり・首こり、またそこから波及して起こる頭痛などに
対する施術・リハビリに携わって来たセラピストによる整体です。
当店では、肩だけでなく【体全体のバランス】からアプローチすることで、短期的な解消+長期的な予防を実現しています。
👨⚕️具体的なアプローチの例
頭・肩・骨盤の位置関係を評価し、姿勢のバランスを分析。
肩甲骨など肩周辺の動きや、呼吸・背中・腰の筋肉の連鎖性をチェック。
必要な部分はやさしくゆるめ、働いていない又は間違った動きをしている筋肉の改善を図る。
自宅でできる、セルフケアやストレッチ、姿勢改善方法などをお伝えします。
👐 一緒に“こらない体”をつくっていきましょう!
その場しのぎのマッサージから、「なぜ肩がこるのか」に向き合う整体へ。今身体に起きている事が
わかるから、改善に向かえる。あなたの体とじっくり向き合う時間を、ここで過ごしてみませんか?
🌿まとめ:肩こりに本当に必要なのは…
✔ ただの“リラクゼーション”ではなく、根本改善の視点
✔ “肩だけ”ではなく、姿勢・全身・生活まで見るアプローチ
✔ 国家資格者で様々な経験や研鑽を積んだセラピストだからこそできる、体の仕組みに基づいた分析と施術